「疲れやすくて、気持ちばかりが先走る」
やりたいことがあっても、体調不良で倒れてしまう。
“からだとこころのズレ”にガッカリする日々。
やりたい気持ちはあるのに、挑戦したいことがあるのに、
上向いた気持ちを、まるで身体が引き戻してくるみたいでした。
「このままじゃ前に進めない」と、焦っては過ぎていく日々。
そろそろ、自分の身体を“諦める”しかないのかもしれない。
そんな時に出会ったのが、東洋医学とAIという視点。
手帳で日々の記録を“武器”にしながら、“体質から自分を整える暮らし”を、始めてみることにしました。
整体をきっかけに、東洋医学の視点へ
去年から整体に通うようになって、「全体を見る」視点に触れるようになりました。
例えば肩が痛くても肩を触らない。
首や手首、股関節といった別の場所から整えていく。
「痛みの場所に原因があるとは限らない」、というのが東洋医学の考え方です。
全体を見て身体を整えてもらう経験を重ねるうちに、東洋医学への興味を持つようになりました。
特に私は「胃腸が弱い」と自覚して、整体の先生からも言われていました。
なので、”養生(ようじょう)”という、日常を整える考え方を生活に取り入れてみることにしたのです。
養生(ようじょう):東洋医学で言う「自分の体に合った暮らし方をして、体調を整えること」。日々の食事・運動・感情のバランスまで含めた“生活まるごとのセルフケア”のこと。

健康に必要なのは「食事・運動・睡眠」とよく言われますよね。
東洋医学は全体を見る学問なので、細切れの知識として持っていた「水は一日2ℓ」「週3回は30分以上の運動」「睡眠は7時間以上」のような情報を自分専用に連続したものとして捉えたいと思い、養生生活を試してみました。
あなたは、自分の知識を全体的にまとまったものとして、自分仕様にカスタマイズして活用できていますか?
東洋医学の主治医としてAIを設定してみた
以前も養生についての本は読んだことはありましたが、自分がどういうタイプなのか、よくわかりませんでした。
「”気虚(ききょ)”と”水滞(すいたい)”、両方当てはまる気がするけど、どっちなんだろう?」
と、いつも迷ってばかりでした。
気虚(ききょ):東洋医学でいう“エネルギー不足タイプ”。疲れやすく、冷え・胃腸虚弱などが出やすい傾向がある体質のこと。
水滞(すいたい):体の中に余分な水分がたまってしまうタイプ。むくみ・めまい・頭が重い感じが特徴で、天候の影響を受けやすい人も多い。
そこで、AIに“東洋医学の主治医”としてアドバイスしてもらえるように設定して、
今の体調、食生活、過去の不調、整体の記録等、思いつく限りいろいろ入力してみました。
すると、それまでモヤモヤしていた身体の反応に対して、
「あなたのタイプなら当然の反応ですよ」
「むしろ、身体が正直にサインを出してくれていて、デトックスする力があるタイプです」
と返ってきて、私の身体がおかしいのではないとわかり、肩の力がふっと抜けました。
「2時間のお昼寝」も、ダメじゃなかった
例えば、私は疲れやすくて、
「お昼寝は”パワーナップ”の効果を得られる20分だけ」のつもりが、気づいたら2時間寝ていたりします。
パワーナップ:午後のパフォーマンスを高めるためにとる短時間の昼寝のこと。一般的には15〜30分以内が推奨され、脳や身体の回復に効果的と言われている。
起きた後に自己嫌悪になっていたけれど、
「ここ数日、気圧の変化が激しくて眠気がひどいんだけど、対処法はある?」と条件を入れて聞いてみると、
「この時期は水滞タイプの方には特につらいですね。朝に○○茶、昼に△△を食べてみるのがおすすめです。夜は××の呼吸法も効果的です。」と返してもらえる。
その冷静な優しさと今後に向けてのアドバイスに、自責に傾きがちな思考が止まり、すごく救われました。
記録と振り返りのパートナーとしての“手帳”
自分仕様のアドバイスを得るために、日々の手帳の記録が役に立ちました。
食事や体調、気圧や睡眠などの記録、その時感じたこと、試してみたこと、合わなかったこと。
それらをバーチカル手帳の1時間ごとの時間軸に、「予定・行動・体調・感情・気づき」に分けて書いています。
夜に手帳で1日の振り返りをしていると、ふと「この行動がお昼寝に影響しているのかも?」と気付き、AIに相談することができます。
また、できるだけ毎日書いているので、数週間分の過去を振り返って「ジムがある日の食事のタイミングを変えるのはどうかな?」と振り返ることもできます。
日中は手帳に記録(行動・体調の二つ)をとっておくと、振り返りで使用でき、AIからのアドバイスの内容も精度が上がります。
この“観察→仮説→検証”をくり返していると、
これまでバラバラだった自分の身体と心が、少しずつ繋がっていく感覚がありました。
こうして、手帳は「記録する場所」だけでなく、「自分の身体と気持ちを整える場所」にもなりました。
AIだからこそ、遠慮なくいつでも相談できる
なんといってもAIの良いところは、いつでも何度でも、気になる時に聞けること。
人間相手では、そうはいきませんよね。
そして、これまでの思いつく都度の会話の内容全てを踏まえて、アドバイスをもらえます。
例えば、
「私の体質に合う食事は?冷蔵庫にある材料はコレ」
「今の私に必要な運動・睡眠・食事についてまとめてスケジュールにして」
「少しだけのつもりが、長くお昼寝してしまった。今週何にも続いてるけど大丈夫?」など、
自分の暮らしに合わせて何度でも私仕様にカスタマイズされた相談ができるのです。
実際に私は整体の先生に健康相談しますが、限られた時間の中でしかできないので、日常で思いついた都度の相談はできません。
なので、補完としてのAI活用は大いにアリだと感じています。

もちろん、AIの回答は絶対の正解ではありません。
でも、これまでの自分の経験と専門家(整体の先生)の意見等を踏まえて、プラスアルファの「自己管理ツール」として使うのであれば、とても良いと感じます。
実際に体に合わない食材や行動を提案されても、そもそも健康被害のないような行動や食材であれば、「お試し」と思って取り入れても損はないと思います。
何より自分の身体に関心が向くことの効果が大きいと感じます。
自分の大切な、一生お世話になる身体への理解を深めるツールとして、使ってみるのはアリだと思いませんか?
私の性格と体質は、つながっていた(育った環境の影響は小さかった)
AIに身体のことを相談しているうちに、
「性格って、生育環境よりも、体質の影響が一番大きいんじゃないか?」と思うようになりました。
試しにAIに聞いてみると、
「胃腸が弱い人は、慎重で頑張りすぎる傾向がある」
と言われました。
これまでの経験や自己診断ツール等で知った自分の特徴と合致していて、驚きました。
自己啓発系の本では、性格については家庭環境の影響が大きいから「親との関係性の棚卸し」ワークがよくありますが、私は何度ワークをしてもピンときませんでした。
親は私の価値観の表面(モノの見方、考え方)に影響を与えていても、私そのものを構成する根本的な価値観への影響があるようには、感じられませんでした。
でも、「体質がベースにあって、環境で補正されたもの」という見方をしたら、
ものすごく腑に落ちたんです。
長年の違和感が消えて、自分への理解が大きく進んだように感じました。

親ワークが苦手だった理由は、「親が○○だったから」と今現在の不満を親のせいにして、「私は悪くない」という現状で止まるような気がしていたからです。
もちろん、その視点も大切だと思います。
でも、「その次は?どう変えたい?」という自分からの改善行動につながらずに、私は止まってしまいました。
なので、あくまで私の場合ですが「体質からのアプローチ」で初めて納得できました。
誰もが親との関係性ではなく、体質の方が影響が大きいとは限りませんが、「もうひとつの見方」として参考になれば嬉しいです。
私という木の「葉っぱ」じゃなく、「幹」や「根っこ」を知る感覚
自分の感情がわからなくなってからこの一年、自己理解に取り組んできました。
その中で、たくさんの私を発見しました。
・やりたい気持ちがあっても、すぐ疲れて寝込む
・気圧や天候、周囲の状況に敏感で、合わないと調子を崩す
・周囲の優しい人に、なぜか頼れない
・「なぜ?」と思うことを深掘りしたくなる
・習慣化は、意志力のいらないよう仕組化する
このように部分的な“葉っぱのような私”を集めていたように思います。
そして、この“葉っぱ”から「私というもの」を客観的に見るために、あれこれ分類しては俯瞰して全体を見る、ということを繰り返していました。
でも、東洋医学を通して自分を知ることで、これまで葉っぱを集めてはどう整理しようか悩んでいたことが嘘のように、ストンと納得できたのです。
まず、体質という“根っこ”がある。
そして、性格という“幹”を通して、
日々の行動という“葉っぱ”を見つめ直す。
すると、一本の木として「私」がつながる感覚がありました。
そうやって、この一年取り組んできた手帳だけでの自己理解ではたどり着かなかった部分に、AIが私を届けてくれたように感じます。

例えば、私という木には——
- 根っこ:胃腸が弱い、水滞体質
- 幹:体質をもとに形づくられた、慎重で頑張りすぎる性格
- 葉っぱ:体力を見積もりすぎて予定を詰めすぎてしまう、日々の行動や思考パターン
このように“体質(根っこ) → 性格(幹) → 行動(葉っぱ)”というつながりを意識することで、ようやく「私というもの」の全体像を客観的に見れたと感じました。
しかも、性格は遺伝の影響が一番大きい、という実験結果とも合致していて、やっと「納得できた」と思いました。
おわりに:自分の“ペース”で“ベース(体質)”を整えていく
“みんなと同じように動ける身体”を目指すのではなく、
「今の自分の身体に合った生き方」を選ぶ時期が来たのかもしれない。
そんなときに出会ったのが、東洋医学の「養生」の考え方でした。
「体力があっていいな」と羨んでいた。
でも、誰かの身体と交換できるわけじゃない。
劇的に変えることはできなくても、今より少しだけラクになる方法は、きっとある。
無理に“みんなと同じ”を目指すんじゃなくて、
私の身体に合った暮らしを、少しずつ整えていけばいい。
もう、大切な身体に無意味な鞭は打ちたくない。
完璧じゃなくていい。
心では動きたいのに、身体がついてこない日もある。
変化の少ない日々に、焦ることもある。
でも、その地道な“自分との対話”こそが、人生を動かす力になる。
そう思える日が、きっと来ると思うから。
私が使っている3つのツール
- AI:自分仕様の“相談相手”として使えるツール
- 東洋医学:体質ベースの自己理解の土台
- 手帳:自分の変化と整える力を引き出すパートナー
この3つの道具を使って、無理のない“私仕様”の暮らしを組み立てていく。
その実践の記録を、これからも綴っていきます。
追記|AIとのつきあい方について

今回、AIは東洋医学の相談相手として紹介しましたが、設定次第で他にも…
- 心の壁打ち相手(心理カウンセラー)
- パーソナルジムのトレーナー(食事指導、生活習慣も含む)
- 読書家の友人(著名な人であればネット上にその人の情報があるので、それを踏まえて友人になってくれる)
みたいに、自分の理想の相談役に育てていけるツールだと感じています。
これからのAIの未来に、複雑な気持ちもあるけれど。
「使われる」ことで終わらず、ちゃんと“使いこなせる人”でいたい。
そのためにも、これからも自分の手で触れて、試して、考えていこうと思います。
「もう少し疲れにくい身体だったら…」
そう思ったことがあるあなたへ。
自分の身体と心に、あなた仕様の方法で、そっと向き合ってみませんか?
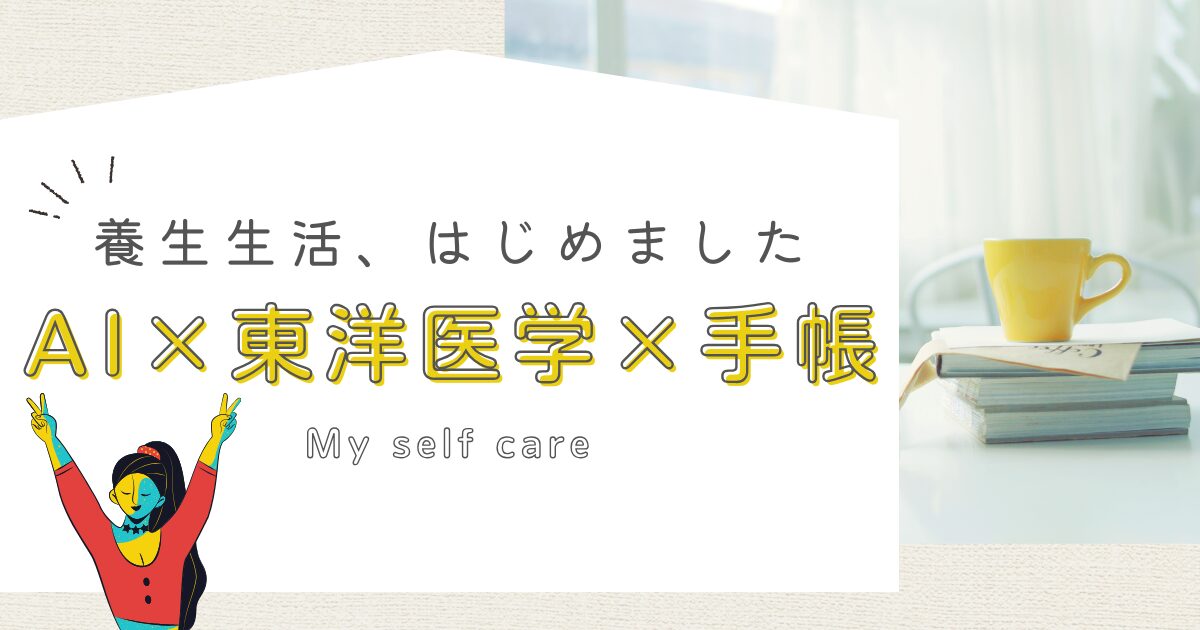


コメント